本文
科学館スタッフによる広報がまごおりコラム「生命の海から」
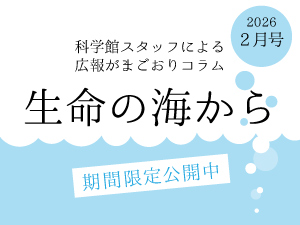
空を見上げて
届かぬ手紙を待ちながら…
「雪は天から送られた手紙である」とは、物理学者にして随筆家の、中谷宇吉郎(なかやうきちろう)の言葉です。結晶が見せるさまざまな形が、気温や水蒸気の量など、雪の故郷である上空の大気の状態を反映していることを指しています。
天からの手紙は届くとたちまち融けて、残るのは小さな滴、水です。水の分子は酸素ひとつに水素が二つぶら下がったような、まるでヤジロベエのような形をしています。水が凍るときには、たくさんのヤジロベエが手をつなぎ合い、自然に六角形を形作っていきます。六花ともいわれる雪の結晶の形の源は、水分子の性質にあるのです。雪だけでなく、池にはる氷や窓を縁取る霜に見られる幾何学模様は、極小の、原子や分子の世界の映し絵なのです。
雪や氷の形だけでなく、水のさまざまな性質も、極小の世界に由来しています。例えば、水は様々な物質を溶かし込むことができますが、これは水の分子がプラスとマイナス両方の電気を帯びた“双極子”としての性質をもつためです。おかげで私たちは、たっぷりのお砂糖を溶かし込んだ甘い紅茶を楽しめるというわけです。さらに言えば、もしも水が生命の素材である有機物を溶かし込むことができなかったなら、海で生命が誕生することはなかったでしょう。
自然の中で、雪、霜、氷、滴など水のさまざまな姿を同時に眺められるのは、冬ならでは。ぜひ、間近で観察してみてください。(寒いのが難点ですが…)

天からの手紙、雪の結晶。
生命の海科学館 館長 山中 敦子
(2026年2月1掲載)
>> 広報がまごおりについての詳細はこちら(蒲郡市広報がまごおりのページが開きます)

