本文
後期高齢者医療制度〔受けられる給付〕
このページでは、後期高齢者医療制度で受けられる給付についてお知らせしています。
医療を受けるとき
医療機関で診療を受けるときは、保険の資格確認ができるもの(保険証利用登録のされたマイナンバーカード、資格確認書等)を窓口に提示します。かかった医療費の一部を自己負担金として窓口で支払います。
医療費の患者負担割合および負担区分
自己負担の割合は、世帯の前年の所得をもとに、8月から翌年7月までの判定をします(毎年、所得の状況により判定します)。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月にさかのぼって再判定します。
| 負担割合および負担区分 | 判定基準 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3割負担 | 現役並み所得3 | 同一世帯に住民税の課税所得が、690万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | ||
| 現役並み所得2 | 同一世帯に住民税の課税所得が、380万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | |||
| 現役並み所得1 | 同一世帯に住民税の課税所得が、145万円以上ある被保険者がいる世帯の方 | |||
| 2割負担 | 一般2 |
住民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する世帯の属する被保険者の方(現役並み所得者を除く。)
|
||
| 1割負担 | 一般1 | 現役並み所得1、2、3、一般2及び住民税非課税世帯のいずれにも該当しない方 | ||
| 区分2 (住民税非課税世帯) |
被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税の方で、区分1に該当しない方 | |||
| 区分1 (住民税非課税世帯) |
被保険者の属する世帯の世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方 | |||
ただし、3割負担と判定された方でも次に該当する場合は、申請により翌月から1割または2割負担となります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
- 同一世帯に被保険者が1人のみの場合で、収入の額が383万円以上あり、同じ世帯の70歳以上75歳未満の方との合計収入額が520万円未満のとき
また、現役並み所得のある方のうち、次の条件のいずれにも該当する場合は、「一般1」(1割負担)または「一般2」(2割負担)の負担区分が適用されます。
- 同じ世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる。
- 同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(※)の合計額が210万円以下である。
※旧ただし書所得とは、所得金額から基礎控除額を控除した金額です。所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。
入院時食事療養費
入院したときは、標準的な食事の費用のうち、下記の「食事代の自己負担金」 を病院等の窓口でお支払いいただきます。
| 区分 | 自己負担金(1食当り) | |
|---|---|---|
| 現役並み所得者および一般(市県民税課税世帯) | 510円 (注1) | |
| 指定難病患者の方(下記に該当しない方) | 300円 | |
| 住民税非課税世帯等 | 90日までの入院 | 240円 |
| 90日を超える入院(愛知県後期高齢者医療加入前の入院も含め、申請月から過去12か月間の入院日数) | 190円 | |
| 所得が一定基準に満たない世帯(各種の所得(注2)の金額がいずれも0円となる世帯) | 110円 | |
(注1) 令和7年3月までは1食につき490円。また、平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円
(注2) 公的年金は控除額を80.67万円で計算
市民税非課税世帯等の方は、限度区分の記載された「資格確認書」を交付しますので、手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 保険の資格確認ができるもの(保険証利用登録のされたマイナンバーカード、資格確認書等)
- 申請者の身分証明書
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 90日を超える分の領収書(90日を超える入院をされている方)
※資格確認書は毎年8月に更新を行います。引き続き該当となる方については、7月に新しい資格確認書を郵送します。
※マイナ保険証を利用された方については、申請不要で自己負担限度額が適用されます。
△上に戻る
入院時生活療養費【療養病床に入院した場合】
療養病床に入院する方については、食費のほかに居住費についても定額を負担していただくことになります。
ただし、難病など入院医療の必要性の高い方については、自己負担の軽減処置が図られ、食事代のみを負担することになります。
| 区分 | 食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) | |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者および一般(住民税課税世帯) | 510円 | 370円 | |
| ※470円 | 370円 | ||
| 住民税非課税世帯等 | 非課税世帯(区分2) | 240円 | 370円 |
| 非課税世帯(区分1) | 140円 | 370円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | |
※一部の医療機関では、470円の場合があります。
※区分についてはページ上部「医療費の患者負担割合および負担区分」参照。
住民税非課税世帯等の方は、限度区分の記載された「資格確認書」を交付しますので、 手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 保険の資格確認ができるもの(保険証利用登録のされたマイナンバーカード、資格確認書等)
- 申請者の身分証明書
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
※資格確認書は毎年8月に更新を行います。引き続き該当となる方については、7月に新しい資格確認書を郵送します。
※マイナ保険証を利用された方については、申請不要で自己負担限度額が適用されます。
△上に戻る
医療費が高くなったとき【高額療養費の支給】
高額療養費については「後期高齢者医療(高額な医療等を受けられる方へ)」をご覧ください。
高額療養費の特例(特定疾病)
厚生労働省指定の特定疾病の方で長期にわたり高額な医療費がかかる場合は、 病院等の窓口で「特定疾病療養受給証」を提示すれば、一部負担金の限度額が月1万円になります。
対象となる病気(特定疾病)
- 人工透析を受けている慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
△上に戻る
高額医療・高額介護合算制度
1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、過重な負担とならないように、一定の支払限度額が設けられており、この限度額を超える場合には、その超えた額が、高額介護合算療養費として支給されます。
△上に戻る
対象となる医療費などの自己負担額について
算定の対象となる自己負担額は、それぞれ次のとおりです。
後期高齢者医療
高額療養費と同様です。 自己負担限度額(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
自己負担限度額(愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページへ)
なお、高額療養費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。
介護保険
介護保険の高額介護(予防)サービス費と同様です。
なお、高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合は、その額を控除した額となります。
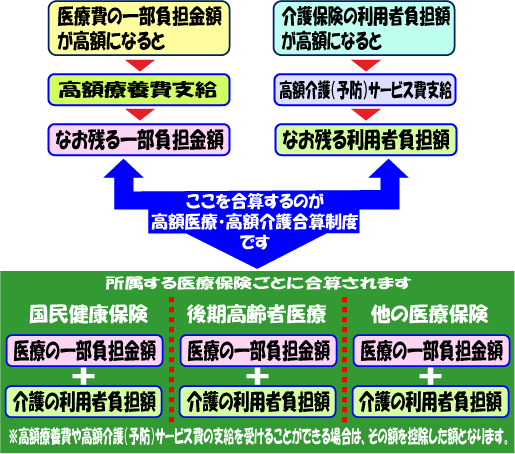
△上に戻る
自己負担限度額
| 区分 | 自己負担限度額 (後期高齢者医療制度+介護保険) |
|
|---|---|---|
|
現役並み所得者(課税所得690万円以上) |
212万円 | |
|
現役並み所得者(課税所得380万円以上) |
141万円 | |
|
現役並み所得者(課税所得145万円以上) |
67万円 | |
| 一般 | 56万円 | |
| 住民税非課税世帯 | 区分2 | 31万円 |
| 区分1 | 19万円 | |
※区分についてはページ上部「医療費の患者負担割合および負担区分」参照。
△上に戻る
申請の仕方(ご用意いただくもの)
次のものをご用意いただき、保険年金課までお越しください。
- 保険の資格確認ができるもの(後期高齢者医療と介護保険の両方)
- 申請者の身分証明書
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 銀行等の口座番号がわかるもの(本人名義の口座ではない場合は委任状が必要になります)
- 計算期間内に後期高齢者医療以外の医療保険(蒲郡市の国保など)に加入していた場合は、その時加入していた医療保険の窓口へも高額介護合算療養費の支給申請の手続きが必要になります。この申請を行うと、自己負担額証明書が交付されますので、この証明書を持参して手続きにお越しください。
△上に戻る
災害等による一部負担金免除制度
制度の概要
災害により住んでいる持ち家に著しい損害を受け、医療機関の窓口で医療費の一部負担金(自己負担金)を支払うことが困難な方に、その一部負担金を一定期間免除します。
対象となる方
災害、風水害、その他これらに類する災害により住んでいる持ち家に著しい損害を受け、下記のいずれかに該当する方
- 災害によって著しい損害を受けたことにより属する世帯の世帯主が市民税を減免され、または生活保護の要保護者になった場合
- 属する世帯の世帯主に市民税が課されていない方または市民税が減免されている方
※火災については、その原因が天災、類焼、不審火など被保険者または同居の家族に過失がない火災に限って「災害」として取り扱います。
免除の期間
| 要件 | 期間 |
|---|---|
| 住宅の被害割合が5割以上(全壊・全焼等) | 6か月以内 |
| 住宅の被害割合が2割以上5割未満(半壊・半焼等) | 3か月以内 |
免除の対象とならない一部負担金等
下記のものは免除の対象となりません。
- すでに医療機関の窓口で支払った一部負担金
- 柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術や治療用装具等の療養費にかかる一部負担金相当入院時食事療養費、入院時生活療養費にかかる標準負担額
申請の受付
必要な書類を添えて、保険年金課へ申請をしてください。
▼持参していただくもの
- 保険の資格確認ができるもの(保険証利用登録のされたマイナンバーカード、資格確認書等)
- 被害状況が確認できるり災証明書または被災証明書
△上に戻る
療養費
次のような場合は、いったん医療費を全額支払っていても、申請により保険適用分の9割、8割、7割相当額(治療用装具については基準額の9割、8割、7割相当額になる場合があります。)が払い戻されます。必要な書類を添えて、保険年金課へ申請をしてください。
なお、申請から支払いまで2,3か月余りかかりますので、ご了承ください。
| 事由 | 必要な書類 (ほかに保険の資格確認ができるもの・申請者の身分証明書・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等) もお持ちください。また、銀行等の口座番号がわかるもの(本人名義の口座ではない場合は委任状が必要になります) もご用意ください。) |
|---|---|
| 1.急病など、やむを得ない事情で保険証を出さずにかかったとき | ・支払った費用の領収明細書 |
| 2.コルセットなど治療用装具をつくったとき、または輸血したとき | ・医師の意見書 ・装着証明書 ・代金の領収明細書 |
| 3.海外渡航中、急病などにより治療を受けたとき(海外療養費)(注) | ・医療機関の発行する治療内容や費用の分かる書類(診療内容明細書、領収明細書等) ・上記書類が外国語で書かれている場合は、その翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載したもの) |
| 4.医療機関に資格証明書を出して治療を受けたとき(特別療養費) | ・領収書 |
注)海外療養費の支給額は、国内で保険診療を受けた場合に準じた金額で算定します。 また日本円換算には、支給決定日の外国為替換算率を用います。
△上に戻る
移送費
負傷した患者を災害現場から医療機関に緊急に移送した場合、移送費が支給されます。保険の資格確認ができるもの・申請者の身分証明書・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)・銀行等の口座番号がわかるもの(本人名義の口座ではない場合は委任状が必要になります)・医師の意見書・移送費用の領収書を添えて、保険年金課へ申請してください。
△上に戻る
保険外併用療養費
保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、この部分については一部負担金を支払い、残りの額は「保険外併用療養費」として後期高齢者医療保険から給付が行われます。
評価療養
保険給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要なもの
- 先進医療
- 医薬品の治験に係る診療
- 医療機器の治験に係る診療 など
選定療養
特別の病室の提供など被保険者の選定にかかるもの
- 特別の療養環境の提供
- 予約診療
- 時間外診療
- 200床以上の病院の未紹介患者の初診
- 200床以上の病院の再診
- 制限回数を超える医療行為
- 180日を超える入院 など
自己負担が1割の方の例
総医療費が100万円、うち先進医療にかかる費用が20万円だったケース
- 先進医療にかかる費用20万円は、全額患者が負担します。
- 通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料など)80万円は、後期高齢者医療保険から保険給付されます。したがって、患者の一部負担金は、8万円となります。
※なお、保険給付にかかる一部負担金については、高額療養費の対象となります。
△上に戻る
訪問看護療養費
難病患者、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病の患者が、訪問看護ステーションを利用して在宅医療を受けたときは、費用の自己負担割合相当額をお支払いいただくだけで、残りを後期高齢者医療保険が負担します。(ただし、オムツ代等は、自己負担。また要介護者については介護保険から給付します。)
△上に戻る
葬祭費の支給
被保険者が死亡したときは、その葬祭をおこなった方に、葬祭費として5万円が支給されます。
葬儀を終えられて落ち着かれましたら、手続きをお願いします。
▼持参していただくもの
- 保険の資格確認ができるもの(保険証利用登録のされたマイナンバーカード、資格確認書等)
- 葬祭をおこなった方の口座番号(郵貯銀行は郵便振替登録済みのもの)
- 会葬礼状または火葬許可証
△上に戻る

 情報をさがす
情報をさがす