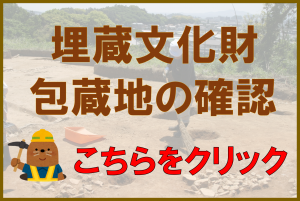ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
検索
本文
蒲郡の歴史と文化財 嘉永七年の大地震
嘉永七年の大地震
今から約160年前、嘉永7年(1854年) 11 月4日・5日に、南海トラフ沿いを震源とする大きな地震が発生しました。
その範囲は関東地方から近畿地方にまで及ぶもので、特に駿河湾の海岸沿いの被害が大きかったようです。
当時、形原村には、旗本・巨勢(こせ)氏の陣屋が置かれていました。その地に伝わっている「形原役所記録」には、
巨勢氏を領主とする村々(蒲郡市域では形原村と西浦村)から地震に関する報告が寄せられています。
4日朝10時頃の地震
- 建物の破損数は多かったが、倒れるほどの被害はなし。けが人もなし。
- 海岸に高波がきて津波を警戒し立ち退きの用意もしたが、追々平常化。
西浦では松島を高波が越えるほどで、衣類や穀物が濡れる被害が5軒。 - 大地震発生までにも度々地震があったため、形原や西浦の人々は心配して野宿をした。
5日夕方の地震
大地震のあと、雷のような鳴音がした。
その後も度々地震が起こり、鳴音も小さくはなりつつも7日になってもやまなかった。
全体の被害は少なかったとはいえ、西浦半島西海岸沖の松島(海抜約1メートル)を越えるほどの
波がきたというのは驚きです。松島にはその名の通り、現在もクロマツが生えていますが、この地震の時
あるいは明治22年(1889年)の水害の際に、多くが流出してしまったといわれています。
昭和6年(1931年)に倉舞港の港湾修築によって、松島南端へと続く防波堤が築かれ、歩いて渡れるようになりました。

西浦村絵図(部分) (個人蔵)

 情報をさがす
情報をさがす