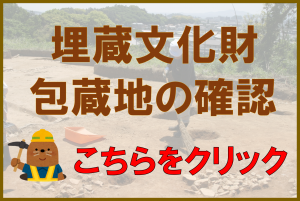本文
展示会履歴
昭和54年の開館から現在までの企画展・特別展を振り返ってみました。
昭和54年度
-
蒲郡の文化財展
- 11月1日から12月26日
岸間コレクション灯火具展
1月5日から3月30日
昭和55年度
-
郷土の文化財展(1)美術工芸
- 1月6日から2月15日 図録
昭和56年度
三河の銅鐸展
- 10月18日から11月8日
三河地方で出土した銅鐸が一堂に会し、研究者の注目を集めました。 -
郷土の文化財展(2)火縄銃
- 3月10日から3月28日 図録
昭和57年度
昭和58年度
-
蒲郡の名刀展
- 11月3日から11月27日
-
新指定蒲郡の文化財展
- 3月17日から3月25日 図録
昭和59年度
-
郵便切手・写真展
- 7月28日から7月29日
蒲郡市制30周年を記念して催されました。 -
古地図に見る蒲郡展
- 11月3日から11月25日
昭和60年度
日本の貨幣展
4月28日から5月12日
灯火具展
6月1日から6月23日
-
西郡松平展
- 3月16日から3月30日
昭和61年度
収蔵品にみる「米作りの農具展」
- 11月1日から11月24日 図録
昭和62年度
- 増改築工事の為 閉館
昭和63年度
-
冷泉家所蔵品展「藤原の雅」・ 東京町田市立国際版画美術館所蔵「近現代の日本版画」
- 4月28日から5月8日
増改築完了記念として、ふたつの展示会を同時に開催しました。 図録「近現代の日本版画」 -
愛知県埋蔵文化財展
- 7月29日から8月7日
-
岡本ケイ吾コレクション ※「ケイ」は金偏に「圭」
- 11月1日から11月27日 図録
-
回想常磐館
- 3月4日から3月26日
-
平成元年度
-
愛知県美術館所蔵 絵画名品展
7月29日から8月20日
沖縄・浦添の文化財
- 11月1日から11月26日
市制35周年記念の企画展。友好提携をしている沖縄県浦添市の貴重な文化財を展示しました。 図録
平成2年度
-
愛知県美術館所蔵「名作展」・シルクロードの灯火具
- 7月20日から8月20日
-
冷泉家の絵巻物
- 11月3日から11月18日
-
蒲郡の絵馬
1月5日から1月27日 図録
-
郷土の画家(1)洋画
- 3月2日から3月24日 図録
平成3年度
-
相撲錦絵展
- 7月7日から7月21日
藤原俊成の古典 【有料】
- 11月1日から11月10日
国宝・重文を含む古筆切の数々を展覧しました。 図録 -
郷土の作家(2)日本画・書・彫刻
- 3月8日から3月22日
-
平成4年度
-
吉野ヶ里展 【有料】
- 11月1日から11月23日
全国的に話題を呼んだ吉野ケ里遺跡の出土品を展覧。講演会も開催。 -
百人一首かるた展 【有料】
1月23日から2月7日
郷土の作家(3)広本三兄弟展
- 3月6日から3月21日
三谷町出身の画家・広本進、季与丸、森雄の3氏の作品をとりあげた。 図録
平成5年度
-
蒲郡の城主
- 11月3日から11月24日
戦国時代の蒲郡を治めていた竹谷松平氏・五井松平氏・形原松平氏および鵜殿諸氏の書状や肖像画を展覧。 -
わが家の家宝展
- 1月25日から2月13日
お宝の価値はひとそれぞれ、思い入れの一品を展示。 -
郷土の作家(4)永島岸翠展
- 3月10日から3月21日
シリーズ第4弾。上ノ郷(現神ノ郷町)出身の画家・永島岸翠の作品を展示。 図録
平成6年度
-
沖縄の美
- 4月8日(金曜日)から5月5日(木曜日)
市制40周年記念として、沖縄県浦添市の漆器や織物を紹介しました。 図録 -
秋山庄太郎写真展「薔薇」
- 4月20日(水曜日)から5月1日(日曜日)
さまざまな表情を見せる薔薇の写真をギャラリーに展覧しました。 -
40年前の蒲郡
- 7月23日(土曜日)から7月31日(日曜日)
市制が施行された昭和29年前後の日用品や写真パネルで、蒲郡の移り変わりを紹介しました。 -
蟹展
- 8月13日(土曜日)から8月21日(日曜日)
個人所有の貴重な蟹標本のコレクションを展示しました。 -
天桂院什物展
- 11月3日(木曜日)から11月27日(日曜日)
竹谷松平氏菩提寺でもある古刹・天桂院所有の品々を紹介しました。 -
常磐館・蒲郡ホテルの面影
- 12月3日(土曜日)から12月25日(日曜日)
かつて多くの文豪・有名人に愛された宿の調度品やパンフレットを展示しました。 -
蒲郡ライオンズクラブ愛蔵品展
1月13日(金曜日)から1月22日(日曜日)
会員が愛蔵する品々を展示しました。
-
郷土の作家(5)蒲郡の書家
- 3月4日(土曜日)から3月19日(日曜日)
郷土の書家3名の遺作を展示しました。 図録
平成7年度
-
郷土の相撲力士展
- 7月1日(土曜日)から7月23日(日曜日)
この地方で盛んだった草相撲の力士や、蒲郡出身の横綱・玉の海の資料を展覧しました。 -
戦中戦後の蒲郡
- 8月8日(火曜日)から8月27日(日曜日)
戦後50年、時代を物語る品々や写真パネルを展示。 -
描かれた三河湾の魚 山本晃作品による
- 8月9日(水曜日)から8月27日(日曜日)
三河湾にはどんな魚がいるの? 夏休み期間に合わせた子どもたち向けの展示でした。 -
漆と麻縄の美 小泉満作品による
- 9月9日(土曜日)から9月24日(日曜日)
形原のロープを素材に、独自の創作を続ける小泉氏の作品を紹介しました。 -
東三河の古墳 副葬品にみる古墳文化
- 11月1日(水曜日)から11月26日(日曜日)
主と一緒に古墳に葬られた品々を展覧しました。 -
蒲郡で活躍する画家
- 2月3日(土曜日)から2月18日(日曜日)
市内で創作活動をしている作家5名の作品を展覧しました。 -
写真で見る蒲郡の祭
- 3月9日(土曜日)から3月17日(日曜日)
市内各所で受け継がれている祭を写真パネルで紹介しました。
平成8年度
-
蒲郡の鳥
- 8月10日(土曜日)から8月25日(日曜日)
渡り鳥や身近な野鳥の写真パネル、三ヶ根山附近で確認されたハヤブサ関連の資料を展覧しました。 -
三谷祭展
- 9月21日(土曜日)から10月6日(日曜日)
市指定文化財・神船若宮丸(東区)や、普段は山車の上に載っている恵比寿のからくり人形(西区)など、 貴重な資料を展覧しました。 -
収蔵品いろいろ
- 11月1日(金曜日)から 「収蔵品いろいろ」
平成9年度
-
蒲郡駅の思い出
- 6月3日(火曜日)から7月13日(日曜日)
山小屋風の懐かしい駅舎の写真をはじめ、蒲郡駅の移り変わりを紹介。 -
蒲郡の古墳
- 7月15日(火曜日)から8月31日(日曜日)
三月田古墳の模型や、市内古墳の出土遺物・写真パネル等を展示。本物の土器片にさわれるコーナーが好評でした。 -
三河のやきもの(1)八ツ面焼
- 11月1日(土曜日)から11月30日(日曜日)
シリーズ第1弾では、西尾市の八ツ面焼をご紹介しました。 -
写真で見る蒲郡の仏像
- 1月6日(火曜日)から2月15日(日曜日)
-
あの時、こんな催し物が・・・蒲郡のイベントポスター展
- 3月3日(火曜日)から3月29日(日曜日)
博物館・市民会館等の催し物のポスターや、文協まつり・市民文化祭の歴代ポスター、季節ごとイベントごとに作られた観光ポスターなどをギャラリーの壁面いっぱいに展覧。
平成10年度
-
写真で見る「冷泉家の年中行事」
- 4月29日(水曜日・祝日)から5月10日(日曜日)
「俊成祭」に合わせて、冷泉家の雅な年中行事を写真パネル等で紹介しました。 -
三河のやきもの(2)ころも焼
- 7月18日(土曜日)から8月23日(日曜日)
三河のやきものシリーズの第2弾として、豊田市民芸館所蔵資料を展覧。
蒲郡の木
- 8月4日(火曜日)から8月30日(日曜日)
夏休みの子ども向け企画展として、蒲郡の巨樹・名木等を紹介しながら、市内に植生する木を展覧。併せて、来場者のみなさまからも蒲郡の名木情報をお寄せいただきました。
蒲郡の中世
11月3日(火曜日・祝日)から11月29日(日曜日)
蒲郡の中世(平安・鎌倉・室町・南北朝)はどんな時代であったか、市内に伝わる文書・工芸品・歴史資料等で紹介。
-
収蔵絵画展
- 2月17日(水曜日)から3月4日(木曜日)
平成11年度
-
常磐館懐古展 客間にかけられていた軸画50選
- 6月5日(土曜日)から6月27日(日曜日)
常磐館の客間にて、四季に合わせて掛けかえられていた軸画を50幅選び、展覧しました。 -
生活道具にみる山のくらしと海のくらし
- 8月3日(火曜日)から8月29日(日曜日)
設楽町など奥三河地方の山のくらしの道具と、蒲郡地方の海のくらしの道具を比較展示しました。 -
岡本コレクション Part2
- 11月2日(火曜日)から11月28日(日曜日)
多種多様な収集品の中から、第1回目で紹介できなかったものを中心に展示しました。 -
写真で巡る蒲郡の寺七十七ヶ寺
- 3月4日(土曜日)から3月26日(日曜日)
市内77ヶ寺の山門や本堂などを写真パネルで展示しました。
平成12年度
-
蒲郡の古代遺跡
- 6月3日(土曜日)から7月2日(日曜日)
市内の遺跡を、写真パネルや出土品で紹介しました。 -
郷土の昆虫あれこれ
- 8月1日(火曜日)から8月27日(日曜日)
蒲郡市近辺で観察できる身近な昆虫を、標本で紹介しました。 -
竹谷松平代々
- 11月1日(水曜日)から11月26日(日曜日)
郷土の領主・竹谷松平の周辺を展覧し、徳川との関わりを紹介しました。 -
三河のやきもの(3)渥美焼
- 12月2日(土曜日)から12月24日(日曜日)
シリーズ第3弾として渥美焼を紹介しました。 -
写真でめぐる蒲郡の神社
- 2月6日(火曜日)から2月25日(日曜日)
前年度の寺院に続いて神社を紹介しました。
平成13年度
-
写真で見る蒲郡の野草
- 7月18日(水曜日)から8月26日(日曜日)
市内のいたるところで普段何気なく見かける野草の写真を展覧しました。
観光蒲郡の歴史
- 9月22日(土曜日)から10月21日(日曜日)
明治末から大正期頃より中京圏のリゾート観光地として著名になった「観光蒲郡」のあゆみを展覧。 -
東三河の弥生環濠
- 11月3日(土曜日・祝日)から12月9日(日曜日)
平成13年3月に発掘調査が行われた赤日子遺跡(神ノ郷町)の環濠をはじめ、東三河地方で確認されている弥生遺跡の環濠を紹介しました。 -
風景写真でみる蒲郡の移り変わり
- 2月5日(火曜日)から2月24日(日曜日)
風景写真が語りかける蒲郡の今昔を展覧しました。 図録
平成14年度
-
空から見た蒲郡の移り変わり
- 7月23日(火曜日)から9月1日(日曜日)
蒲郡地域の航空写真を部分的に拡大したり、地図と対照できるようにしたりし、普段なかなか見られない空からの視点で、蒲郡の移り変わりを展覧しました。 -
収蔵絵画展
- 10月29日(火曜日)から12月1日(日曜日)
新たに寄贈された作品を含む、蒲郡を描いた作品・蒲郡ゆかりの作家の作品など27点を展覧。 -
なつかしい道具
- 2月15日(土曜日)から3月23日(日曜日)
この頃では使われなくなり、名称すら忘れられた道具を紹介。
平成15年度
-
なつかしいオモチャ大集合!
- 7月19日(土曜日)から8月31日(日曜日)
昭和30年代のオモチャや遊びの道具を展覧しました。 -
農具にみる蒲郡の農業
- 9月30日(火曜日)から10月26日(日曜日)
JA蒲郡のご協力を得て、人や牛馬の力で行ってきたかつての蒲郡の農業と、トラクターなどを使う今の農業との違いを比較展示しました。 -
蒲郡の道 今と昔
- 2月21日(土曜日)から3月22日(日曜日)
風景写真で見る蒲郡の移り変わりシリーズ第2弾。絵図に描かれている古道、江戸時代の街道、現代の幹線道や愛称ロードなど、蒲郡の道の今昔を図や写真で紹介。 図録
平成16年度
-
コーナー展示 水藤澄子 寄贈絵画展
- 6月5日(土曜日)から6月27日(日曜日)
このほど市へ寄贈された絵画9点を展示。初期のスケッチ作品から最近の抽象画まで、氏の中央画壇での活躍の一端を紹介しました。 -
愛知県美術館 平成16年度 移動美術館
- 7月3日(土曜日)から8月8日(日曜日)
愛知県美術館・財団法人愛知県文化振興事業団の「移動美術館」事業。市制50周年記念として、愛知県美術館の収蔵作品の中から約40点を展示。 -
アマチュアカメラマンがみつめた蒲郡の表情50年 牧真太郎記録写真展
- 2月11日(祝日)から2月27日(日曜日)
風景写真で見る蒲郡の移り変わりシリーズ第3弾。市内在住のアマチュア写真家・牧氏が仕事のかたわら50年にわたって撮り続けた蒲郡の風景や人々の表情等約200点を展示。 図録
平成17年度
-
蒲郡のチラシ・広告あれこれ
- 11月1日(火曜日)から12月4日(日曜日)
戦前の古い広告や、近年の大型店舗・個人店舗のチラシなどをテーマ別に展示。 -
EXPO2005記念企画 ありがとう愛・地球博 あの感動をもう一度
- 12月14日(水曜日)から12月25日(日曜日)
愛知万博と蒲郡との関わりを中心に、さまざまな事業やその成果を紹介しました。 -
蒲郡の交通 鉄道高架開通記念
- 2月1日(水曜日)から2月26日(日曜日)
風景写真で見る蒲郡の移り変わりシリーズ第4弾。平成17年12月18日にJR上り線の鉄道高架が開通したのを記念し、鉄道・バス・観光船やロープウェイ等、さまざまな交通に関する資料と写真を展示しました。 図録
平成18年度
-
市史発刊記念企画展 蒲郡の歴史を語る資料
- 7月25日(火曜日)から8月27日(日曜日)
原始古代から現代まで、時系列に沿って、蒲郡の歴史を語る上でその時代の特徴をよく示す資料を展示しました。 -
蒲郡の漁業
11月1日(水曜日)から12月3日(日曜日)
収蔵資料を中心に、打瀬船の時代から今の蒲郡の漁業を展覧。
-
6・3制実施60周年記念 蒲郡の学校
- 2月1日(木曜日)から3月4日(日曜日)
風景写真で見る蒲郡の移り変わりシリーズ第5弾。教科書・給食食器の変遷や、二人掛けの木製机・腰掛などを展示しました。 図録
平成19年度
-
再発見!ふるさとの歴史(1)大塚地区
- 7月31日(火曜日)から9月2日(日曜日)
郷土資料を地区別に紹介する企画展の第1弾。地元ゆかりの古文書・くらしの道具・考古資料等で大塚地区の歴史を紹介しました。 -
海辺の文学記念館開館10周年記念事業企画展 蒲郡の句碑・歌碑
- 10月6日(土曜日)から10月28日(日曜日)
市内の句碑・歌碑について、写真パネル等で紹介しました。 図録 -
帰ってきた広本季与丸展
- 11月1日(木曜日)から12月2日(日曜日)
本年度寄贈を受けた12点および市内公共施設所蔵の季与丸作品を、一堂に会して紹介しました。
平成20年度
-
地面の下には何がある? 発掘調査入門
- 8月1日(金曜日)から8月31日(日曜日)
発掘調査とはどういうものか。発掘調査から何がわかるのか。出土資料や発掘風景写真、発掘用の道具などを用いて紹介しました。 -
日本の切手・世界の切手 芦川コレクションを中心に
- 10月8日(水曜日)から10月19日(日曜日)
観光交流ウィークにあわせ、1階ロビーで国内外の切手コレクションを中心に展示。 -
JR東海さわやかウォーキングタイアップ企画 写真でたどる蒲郡駅の思い出
- 10月11日(土曜日)から11月3日(月曜日・祝日)
山小屋風駅舎・鉄筋駅舎・鉄道高架事業後の現在の駅舎など、蒲郡駅の移り変わりを写真でふりかえりました。
2階研修室で展示しました。 -
再発見!ふるさとの歴史(2)三谷・東部地区
- 11月1日(土曜日)から11月24日(月曜日・祝日)
三谷・東部地区の歴史について、古文書・絵地図・写真・寺社所蔵資料などを通じて紹介しました。 -
蒲郡の自然 春夏秋冬
- 2月7日(土曜日)から3月1日(日曜日)
蒲郡の四季の移り変わりを、写真や剥製など、自然に関する諸資料で紹介しました。 図録
平成21年度
-
伊勢湾台風50年事業 写真でたどる蒲郡の災害
- 9月25日(金曜日)から10月16日(金曜日)
伊勢湾台風襲来50年に際し、本市の地震や台風における災害を写真でたどりました。
市制55周年記念事業 戦争に関する資料館調査会 収蔵資料展
- 10月10日(土曜日)から10月25日(日曜日)
愛知県と名古屋市で設置している「戦争に関する資料館調査会」の巡回展。あわせて当館収蔵の戦争資料も展示しました。 -
市制55周年記念事業 岡本ケイ吾コレクション展 ※ケイは金偏に「圭」
- 11月1日(日曜日)から12月6日(日曜日)
当館収蔵資料のうち市民の間でも関心の高い岡本ケイ吾コレクションを公開しました。
市制55周年記念事業「蒲郡を描く」公募絵画展
- 2月6日(土曜日)から3月7日(日曜日)
蒲郡の特徴を描いた絵画作品を募集。応募作品94点を展示しました。 -
平成22年度
広告でたどる庶民のくらし展 Part1 蒲郡にも映画館があった
- 7月30日(金曜日)から8月22日(日曜日)
- 最盛期には9軒あった映画館のうち、最後(平成12年)まで営業を続けていた「蒲映」の資料を中心に、蒲郡と映画の関わりについて展覧しました。
観光交流ウィーク・コーナー展示
上海万博記念 あの感動をもう一度 愛・地球博と蒲郡
10月9日(土曜日)から10月24日(日曜日) 灯火具と併設展示
三谷祭山車出展風景やフレンドシップ交流など、2005年に開催された「愛・地球博(愛知万博)」の資料を通して当時を振り返りました。
広告でたどる庶民のくらし展 Part2 憧れの電化製品
10月30日(土曜日)から11月28日(日曜日)
憧れの品から実用品へのあゆみをたどったさまざまな電化製品、店頭に置かれたキャラクターや広告チラシ等を展示しました。
広告でたどる庶民のくらし展 Part3 サミゾチカラコレクションの世界
2月4日(金曜日)から2月27日(日曜日)
サミゾチカラコレクションから、ホーロー看板をメインにすえつつ、木製看板・売薬さんのチラシ・空き缶・菓子箱・仁丹資料などなど、摩訶不思議なサミゾワールドを展開。佐溝力氏の講演・えぐれ笹島氏のウクレレ漫談のイベントも行いました。
-
平成23年度
蒲郡市消防本部発足50年「蒲郡消防のあゆみ」
- 8月12日(金曜日)から9月11日(日曜日)
- 平成22年4月に新消防庁舎へ移転した際に寄贈された資料を中心に展示しました。
- 8月11日(土曜日)から9月2日(日曜日)
- 大正時代の資料・写真パネルなどを展示しました。
-
「蒲郡を訪れた有名人の色紙展」
10月5日(土曜日)から10月21日(日曜日)
文化講演会などで蒲郡を訪れた有名人の記念色紙を一堂に展示しました。 - 4月13日(土曜日)から4月21日(日曜日)
- ふるさとのまちと、人々の様子を写したなつかしい写真を展示。
-
企画展「蒲郡のえかきさん」
7月20日(土曜日)から9月1日(日曜日)
蒲郡ゆかりの作家が描いた絵画作品を展示しました。 - 4月1日(火曜日)から5月6日(日曜日)
- 今年60周年(還暦)を迎える蒲郡市60年の歴史に関する展示。
-
企画展「西浦の歴史」 (※再発見!ふるさとの歴史(4))
8月1日(金曜日)から8月31日(日曜日)
西浦の歴史を各種貴重な資料によって紹介しました。 -
平成27年度
徳川家康没後400年記念企画展「天桂院の文化財 -竹谷松平家の歴史-」
-
8月1日(土曜日)から8月30日(日曜日)
天桂院のご協力を得て、同寺ならびに竹谷松平家に関する展示を行いました。戦後70年 夏休み戦争関連スタンプラリー コーナー展示「戦地からの手紙」
-
7月18日(土曜日)から8月30日(日曜日)
豊橋・蒲郡・豊川・田原の文化施設間で実施する
スタンプラリーに合わせて、戦争に関するコーナー展示を行いました。企画展「永島岸翠とその時代」
-
10月24日(土曜日)から11月23日(月曜日・祝日)
郷土出身の画家、永島岸翠の作品を展示。企画展「近代文書にみる蒲郡の歴史」
-
2月27日(土曜日)から3月21日(月曜日・祝日)
蒲郡市博物館所蔵の近代文書(明治から戦前にかけて作成された文書)を展示。 -
平成28年度
没後50年企画展「岸間芳松さんと灯火具コレクション展」
-
7月29日(金曜日)から8月28日(日曜日)
重要文化財「灯火具コレクション」を市へ寄贈してくださった岸間芳松さんを紹介。
館内に、昔の部屋の明るさを再現した体験コーナーを設けました。 -
夏休みミニ企画展「妖怪になった道具たち」
-
7月29日(金曜日)から8月28日(日曜日)
「百器夜行絵巻」等に登場する妖怪のもとになったくらしの道具たちを展示。企画展「蒲郡の古墳」
-
10月28日(金曜日)から11月27日(日曜日)
蒲郡の古墳に関する企画展。出土した遺物や遺構図面などを展示。
発掘調査報告書を刊行・販売。企画展「形原の歴史」 (※再発見!ふるさとの歴史(5))
-
2月24日(金曜日)から3月20日(月曜日・祝日)
形原地区の歴史と魅力を紹介。 -
コーナー展「広本進寄贈作品展」
-
3月25日(土曜日)から4月16日(日曜日)
蒲郡市三谷町出身の日本画家・広本進氏のご遺族からご寄贈を受けた
絵画作品9点を展示。平成29年度
コーナー展示「教育のあゆみ」
- 4月22日(土曜日)から平成30年3月31日(土曜日)
昭和22年の教育基本法制定から70年が経過。
教育に関する各種資料(古写真・むかしの教材など)を展示。企画展「ほしかった 夢中になった 昭和のオモチャたち」
7月29日(土曜日)から9月3日(日曜日)
なつかしのオモチャをたくさん展示。昭和の楽しい雰囲気いっぱいの企画展。
オモチャコレクター・山崎隆弘さんの全面協力で開催。
観光交流ウィーク企画展
「アメリカズカップとエリカ号」
10月5日(木曜日)から10月23日(日曜日) 灯火具と併設展示
今春惜しまれながら解体されたエリカ号、駅前に展示されているアメリカズカップのニッポンチャレンジ艇など、海のまち蒲郡に関係する資料を展示しました。
蒲郡ライオンズクラブ創立50周年タイアップ事業
「わが家のお宝展」
10月29日(土曜日)から11月20日(日曜日)
市民愛蔵の、先祖伝来の品や思い出の品を募集し、一同に展示しました。
調査報告書〈1〉発刊記念
「上ノ郷城跡発掘調査速報展」
3月10日(土曜日)から3月25日(日曜日)
これまでの発掘調査の結果をまとめた報告書の刊行にあわせて、出土品などを展示しました。会場には上ノ郷城の復元模型を設置しました。
平成24年度
大正100年記念「大正時代の蒲郡展」
「クラシックカメラの世界」
11月1日(木曜日)から11月25日(日曜日)
個人収集のアンティークカメラコレクションを中心に名機の数々を展示しました。
鮮明写真で蘇る
「明治・大正・昭和 思い出の蒲郡展」
1月5日(土曜日)から1月20日(日曜日)
蒲郡の町なみ・風景などを写真パネルで振り返りました。企画展にあわせて写真集を刊行しました。
平成25年度
ミニ写真展「なつかしのまちかど」
企画展「駅と町なみの移り変わり」 (※再発見!ふるさとの歴史(3))
11月1日(金曜日)から11月24日(日曜日)
蒲郡駅の移り変わりや昔の六間道路のようす、町のにぎわいなどを紹介。
企画展「古文書展 江戸時代の人々の暮らし」
2月1日(土曜日)から2月23日(日曜日)
蒲郡市博物館収蔵の古文書を展示。あわせて文書目録を刊行・販売。
平成26年度
市制60周年記念企画展「祝・還暦!がまごおりモノ語り」
市制60周年記念企画展「蒲郡のあゆみ」
10月28日(火曜日)から11月9日(日曜日)
原始・古代から現代まで、蒲郡のあゆみをたどる展示。
冷泉家時雨亭文庫等から貴重な資料をお借りしました。
企画展「蒲郡の城あと」
2月27日(金曜日)から3月22日(日曜日)
過去の発掘の成果を遺物と写真で紹介する。発掘調査報告書を刊行。
磯部絢子個展 「はじまりのおと」
8月5日(土曜日)から8月13日(日曜日)
「若手アーティスト支援企画」美術作品展
山本千晴個展 「膚はカバンの右奥へ」
8月5日(土曜日)から8月13日(日曜日)
「若手アーティスト支援企画」美術作品展
特別公開「源光寺の仏さま」
9月23日(土曜日・祝日)から10月1日(日曜日)
源光寺(鹿島町)のご本尊「木造十一面観音立像」の修復完了を記念して一般公開。
コーナー展示「マリンスポーツのまち蒲郡」
10月7日(土曜日)から10月22日(日曜日)
アメリカズカップ挑戦の軌跡など、蒲郡における海洋スポーツのあゆみを写真パネル等で紹介。
特別公開「天桂院の涅槃図」
12月16日(土曜日)・17日(日曜日)
天桂院様の所蔵する「涅槃図」が、市の指定文化財に指定されたことを記念して特別公開。
海辺の文学記念館開館20周年記念企画展「常磐館を彩った絵画」
11月3日(金曜日・祝日)から12月3日(日曜日)
常磐館客間にかけられていた掛け軸や、関連資料を展示。
多くの文人墨客などに愛された同館は、観光地・蒲郡のシンボル的存在でした。
企画展「平坂街道をたどる」
3月2日(金曜日)から3月25日(日曜日)
街道のルートを詳細に再現。街道ぞいに所在する貴重な文化財・史跡を紹介。
-
「平坂街道をたどる」解説用冊子 [PDFファイル/1.51MB]
※会場で配布していた冊子です。街道のルートを図示したものです。ぜひご覧ください。
平成30年度
コーナー展示「絵はがき昭和紀行」
- 4月6日(金曜日)から平成31年3月31日(日曜日)
昭和30年代を中心とした地元観光施設の写真パネルや、市内外の絵はがきなどを展示。企画展「塩津の歴史」(※再発見!ふるさとの歴史(6))
- 7月21日(土曜日)から9月2日(日曜日)
塩津地区の歴史を紹介。地元のみなさまの協力を得て、貴重な資料を多数出品しました。山本辰典個展 「忘却の遊戯場」
8月18日(土曜日)から8月26日(日曜日)
第2回「若手アーティスト支援企画」美術作品展 -
収蔵作品展 「愛の画家 広本季与丸」
10月6日(土曜日)から11月4日(日曜日)
蒲郡出身の洋画家・広本季与丸さんの作品を展示。 -
企画展「アカヒコムラ -みかんの下の弥生時代-」
11月10日(土曜日)から12月9日(日曜日)
赤日子遺跡(神ノ郷町)出土資料を中心に、愛知県内の弥生遺跡に関する資料を数多く展示。企画展「昭和のおもしろ道具発明展」
- 2月2日(土曜日)から3月31日(日曜日)
日本屈指の昭和グッズコレクター・佐溝力さんの協力を得て開催。
私たちの生活に密着したアイデア商品などをたくさん展示。
平成31年度(令和元年度)
コーナー展示「家康と戦った城 上ノ郷城 出土品展」
4月6日(土曜日)から令和2年3月31日(火曜日)
2階ロビー
鵜殿氏の本拠地・上ノ郷城は、激戦の末、徳川家康によって攻め落とされた城です。
発掘調査によって城跡から出土した資料(火縄銃の弾丸・焼き物・装飾用の金具)等を展示。
コーナー展示「なつかしの?電化製品」
6月1日(土曜日)から7月15日(月・祝)
特別展示室
電化製品コレクターの方の協力を得て、なつかしの?音響・映像機器を展示。
蓄音機・オープンリール・ワイヤーレコーダー・ロウ管レコード・エルカセット・マイクロカセット・8トラ
VX2000・ユーマチック・ベータ・EDベータ・W‐VHSなど、
親しみのあるもの、あまり広まらなかったものなど、いろいろ出品。
企画展「心にのこる私のふるさと 写真家・近藤四郎さんが写した蒲郡」
7月20日(土曜日)から9月16日(月曜日・祝日)
※当初は9月1日(日曜日)までの予定でしたが、好評につき9月16日まで会期延長し、無事終了。
特別展示室
近藤四郎さんは戦後早くから形原の地で写真館を開業し、ふるさとの写真を数多く写した方です。
没後20年目にあたる今年、四郎さんの写真を通じて蒲郡の昔のすがたを見ることができました。
第3回「若手アーティスト支援企画」美術作品展
植村宏木「漂石と索条」
8月17日(土曜日)から8月25日(日曜日)
1階ギャラリー
現在活躍中の若手作家植村宏木さんの個展を開催。
蒲郡市制65周年・蒲郡市博物館開館40周年記念
「移動美術館2019 こころ、かたどる -あいちの美の双璧、蒲郡へー」
9月21日(土曜日)から10月20日(日曜日)
特別展示室 ・ギャラリー
愛知県美術館・愛知県陶磁美術館の名品を展示。
企画展「明治の地籍図を読みとく -むかしの道といまの道-」
2月15日(土曜日)から3月15日(日曜日)
特別展示室
明治時代に作成された地籍図(ちせきず)を用いて、郷土のむかしの様子や移り変わりを学びました。
蒲郡の史跡や文化財を紹介するマップを作成しました。
令和2年度
コーナー展示 「『同盟写真特報』でみる戦争」
6月13日(土曜日)から7月12日(日曜日)
特別展示室
戦時中に発行された『同盟写真特報』の展示を通じて
当時の世相について考えました。
企画展「-終戦から75年- あの日 あの戦争」
7月18日(土曜日)から8月30日(日曜日)
特別展示室
市民の方からいただいた戦争に関する資料を多数展示。
戦争の悲惨さ、平和の尊さを学びました。
コーナー展示「鈴木茂三郎の手紙と写真」
9月5日(土曜日)から10月18日(日曜日)
特別展示室
蒲郡出身の政治家・運動家で社会党の委員長を務めた鈴木茂三郎氏(1893-1970)は、
日本の労働運動の草分けといえる方です。
没後50年にあたり、茂三郎氏の手紙や写真などを展示しました。
企画展「カケラノチカラ -出土片にみる江戸の暮らしと陶都瀬戸ー」
10月24日(土曜日)から11月29日(日曜日)
特別展示室
江戸時代、蒲郡中心部を治めた松平氏の屋敷(蒲形陣屋)から出土した陶磁器片を展示。
三河各地の城から出土した、同時代の資料も出品、カケラから分かる江戸時代の生活を紹介しました。
また、この時代に県内で大きなシェアを持った「セトモノ」の産地、瀬戸市から、多種多様な製品とともに
窯業生産に使用された道具を展示、やきもの製作の魅力にも迫りました。
【コロナウイルス感染拡大防止のため令和3年度へ延期しました】企画展「昭和の雑誌大集合! -ヤマザキコレクション-」
※延期しました(本来の開催予定は2月6日(土曜日)から3月21日(日曜日))
特別展示室
なつかしの雑誌の展示を通じて、昭和という時代をふり返ります。
著名なコレクター山崎隆弘さんのご協力を得て開催予定。
令和3年度
ロビー展示「1964 東京オリンピックの頃」
4月10日(土曜日)から令和4年3月27日(日曜日)
2階ロビー
第18回オリンピック競技大会の1万メートルに出場した
蒲郡出身の船井照夫氏所蔵資料をメインに、同年開通の
東海道新幹線関連資料なども展示しました。
企画展 「昭和の雑誌大集合! -ヤマザキコレクションー 」
4月24日(土曜日)から7月11日(日曜日)
特別展示室
著名なコレクター山崎隆弘さんのご協力を得て開催しました。
※令和2年度
マンガ・映画・クルマ・芸能・ファッション・野球・相撲・生活・教育などなど、
いろいろなジャンルの雑誌約700点を展示しました。
昭和の熱気あふれる楽しい展覧会となりました。
企画展「松平家ゆかりの文化財」
7月17日(土曜日)から8月29日(日曜日)
特別展示室
戦国時代、蒲郡市内に本拠地があった松平家(竹谷松平家・形原松平家・五井松平家)に
関係する資料を展示しました。
企画展「まる・まわる・まわす -カタチと機能 館蔵民具展-」
10月2日(土曜日)から11月21日(日曜日)
特別展示室
近代以降、蒲郡に生きた人々の暮らしを、時に支え、時に潤した多くの民具たち。
今回は、これらの寄贈された多数の民具から、「まるいモノ・まわるモノ・まわすモノ」を展示しました。
コーナー展示「蒲郡クラシックホテルのあゆみ」
11月27日(土曜日)から2月6日(日曜日)
特別展示室
このたび蒲郡クラシックホテルが国の登録有形文化財に指定されました。
そのことを記念してホテルの歴史を紹介しました。
企画展「ーあの時代を思い出すー なつかしの映画ポスター展」
2月11日(金曜日・祝日)から3月21日(月曜日・祝日)
特別展示室
映画ポスターの展示を通じて昭和という時代の魅力を味わいました。
令和4年度
ロビー展示 「鎌倉時代の蒲郡」
4月9日(土曜日)から12月25日(日曜日)
2階ロビー
大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の登場人物13人全員とゆかりのあった蒲郡。
13人の合議制に名を連ねた御家人の一人、安達藤九郎盛長(あだちとうくろうもりなが)は、
頼朝に従う最古参の側近で、初代三河守護も務めました。
蒲郡市には、その盛長が建立、再興したとされる三河七御堂のうち、
「丹野御堂」「長泉寺」が所在します。また、長泉寺には盛長を供養する五輪塔もあります。
会場では、発掘調査などで出土した資料なども展示し中世鎌倉期の蒲郡を紹介しました。
学制発布150周年記念企画展 「わたしたちの学校」
7月16日(土曜日)から9月25日(日曜日)
特別展示室
学制発布150年を記念した企画展を開催しました。
蒲郡市内全小・中学校20校にも協力を賜り、
貴重な資料や写真をたくさん展示することができました。
会場の前半では、明治〜戦後まもなくまでの蒲郡の学校について展示し、
後半では写真を中心に「学校の一年」を見ることが出来ました。
会期中、記念冊子「わたしたちの学校」を無償配布しました。(限定2500部)
企画展 「旅に詠む 永島拾山と近世三河の歌人・俳人」
10月29日(土曜日)〜11月27日(日曜日)
特別展示室
今回の企画展では「祖翁」松尾芭蕉をはじめとする先達が記した近世の旅日記やその句歌集をとりあげ、
各地の歌枕や歌人・俳人たちの足跡等を辿る旅への想い、旅先での彼らの交遊等を紹介しました。
形原町生まれの俳諧研究者・中村俊定氏の業績も、氏が早稲田大学図書館へ寄贈した
中村俊定文庫の資料と併せて展示しました。
江戸時代末期から明治初期に活躍した神ノ郷出身の俳人・永島拾山が遺した日記には、
京都に庵を構えていた彼が、折々に社寺を参詣したり、郷里へ戻る道すがら各地の仲間の元を訪ねて
盛んに交流したりという日々が克明に綴られています。
筆まめであった拾山の日記・書簡からは、敬けんで信心深い人となりのみならず、
明治という時代の息づかいも感じられました。
無償頒布の解説冊子を配布しました。(限定2000部)
企画展「蒲郡の刀鍛冶〜藤原武則・元久の世界〜」
2月11日(土曜日)から3月19日(日曜日)
特別展示室
藤原武則・元久は、蒲郡市竹谷町で親子2代に渡り刀を作り続けてきた刀鍛冶職人です。
日常生活の中で使われる刃物や農具の製作、修理を行う「野鍛冶」を営みながら日本刀の製作を続け、
やがて日本刀を専門に手掛ける刀匠として名を馳せました。刀の製作過程の映像とともに、
両氏の手がけた日本刀のうち25振を一同に展示しました。
【関連行事】 戸山流居合道東海道場のみなさまにより、居合の演武を披露していただきました。
令和5年度
ロビー展示「家康と戦った城・家康を支えた城 ー発掘調査出土品展ー」
1月7日(土曜日)から令和6年3月24日(日曜日)
2階 展示スペース
令和5年の大河ドラマは「どうする家康」。青年期の家康にとって、蒲郡は大変関わりの深い土地でした。
中世期、蒲郡には9つの城が築かれましたが、うち4つは上ノ郷(神ノ郷町)を本拠とする鵜殿氏の城、3つは家康の一族である松平氏の城で、この地域で両者は拮抗した間柄でした。
展示では蒲郡に居を構えた鵜殿、松平両氏の城跡を発掘出土資料や写真パネルでわかりやすく紹介しました。
コーナー展示 SL展示50年記念「蒲郡駅と鉄道展」
4月1日(土曜日)から7月2日(日曜日)
特別展示室
「はじまりは一人の少年からの手紙だった...」
博物館で屋外展示しているSL「D51201」号が蒲郡にやってきて令和5年度で50年目を迎えます。
これに合わせ、蒲郡駅開業と移転(※蒲郡駅は一度移転しています)、 国鉄マンの仕事道具、SLが蒲郡に来た経緯など、142点の資料で紹介しました。
企画展 「蒲郡戦国年表」
7月15日(土曜日)から9月3日(日曜日)
特別展示室
天文11年(1542)に生まれた竹千代(後の徳川家康)にとって、その後の十数年は、母於大の方との別れ、
父広忠との死別を経て今川配下に置かれた忍苦の時代でした。一方で蒲郡市域においては、度々出陣することはあっても、居城周辺が戦場となることはなく、
比較的平穏な日々を過ごしていたことが資料からうかがえます。
しかし、永禄3年(1506)年5月の桶狭間合戦において今川義元が討たれたことで情勢は大きく変わります。
今回の企画展では市内に伝わる社寺所蔵の資料や竹谷松平家文書を中心に、年代に沿って市域の諸氏の動向を紹介しました。
展示資料の概要がわかる無償頒布の解説冊子を限定2000部で配布しました。
企画展「列車のおもいで 〜鉄道グッズに見る東海の鉄路〜」
10月14日(土曜日)から12月24日(日曜日)
※当初は会期を11月27日(月曜日)までとしていましたが、12月24日(日曜日)まで延長しました。
特別展示室
内容
蒲郡市内在住の鉄道グッズコレクターから、特に東海地方にゆかりのある鉄道に関するグッズを提供いただき展示しました。
同年4月〜7月に開催した「蒲郡駅と鉄道」展では、蒲郡駅にスポットを当てて展示しましたが、今回の展示では、鉄道グッズを通して東海地方の広範囲を扱い、市民の皆様により身近な資料、
また関連した写真を多く掲示し、鉄道を楽しんでいただける内容となりました。
企画展 「館蔵絵画展」
令和6年1月20日(土曜日)から3月24日(日曜日)
特別展示室
当館では、地域に密着した博物館として、「蒲郡出身」「蒲郡で制作活動をしていた」または「蒲郡を描いた」作家の作品を収集保管しています。
今回の企画展では、近年当館に寄贈・移管された絵画作品および市制55周年記念で公募した「がまごおりを描く」入賞作品等、蒲郡にゆかりの絵画作品や関連資料約50点を展示しました。
展示作家(50音順・敬称略)浅井一介、岡本功、小田正春、音部幸司、片野泰人、木下広唯、水藤澄子、廣本季與丸、廣本進、牧野正則、山本定男
令和6年度
企画展 市制70周年記念展示「ひろめる・しらせる 広報から見た蒲郡」
・【第1期】:3月30日(土曜日)〜7月7日(日曜日)
特別展示室、 2階ロビー展示スペース ※1年に渡り3期にわけて展示替えを行いました。
令和6年、蒲郡市は市制施行70周年をむかえました。
今回のコーナー展示(常設展示)では、「広報がまごおり」の紙面を通して蒲郡市70年の歴史を振り返っています。
1階特別展示室では、時系列に沿って蒲郡市のあゆみに関わる記事や広報紙面の移り変わりを、2階ロビー展示ではご時世を感じられるような記事をご紹介しました。
内容:初代・竹内司市長(昭和29年4月)から2代逸見(へんみ)彦太郎市長 (昭和45年2月)までの任期中のできごとについて、 広報紙の記事を中心に展示しました。
・【第2期】:9月10日(火曜日)〜10月14日(月曜日・祝日)
特別展示室、 2階ロビー展示スペース
内容:第3代・長谷部半平市長(昭和45年2月)から第4代 大場進(すすむ)市長 (平成6年2月)までの任期中のできごとについて、 広報紙の記事を中心に展示しました。
・【第3期】:令和6年12月7日(土曜日)〜令和7年2月2日(日曜日)
特別展示室、2階ロビー展示スペース
内容:第5代・鈴木克昌市長(平成6年2月)〜第6代・金原久雄市長 (平成11年11月)〜第7代・稲葉正吉市長(平成23年10月)〜第8代・鈴木寿明(ひさあき)市長(令和元年10月)〜現在までの任期中のできごとについて、
広報紙の記事を中心に展示しました。
上ノ郷城原画展 〜香川元太郎「合戦の城」発刊記念〜
6月25日(火曜日)〜9月1日(日曜日)
1Fエントランスホール
城郭イラストの第一人者、香川元太郎さんのワイド&パノラマ鳥瞰・復元イラスト『日本の城』、同『戦国の城』に続く第3弾、『合戦の城』が、令和6年6月27日に発刊されました。
この中では、蒲郡市の上ノ郷城が所収されており、北から城と三河湾を望むダイナミックな鳥瞰図をごらんいただけます。
今回、『合戦の城』発刊を記念し、上ノ郷城鳥瞰図の原画を初公開しました。
蒲郡市制70周年記念企画展 「がまごおり山ものがたり 〜信仰と観光と〜」
7月20日(土曜日)〜9月1日(日曜日)
特別展示室
令和6年度は、「山の日」制定10周年に当たります(施行は2年後)。
蒲郡は、三河湾に面した長い海岸線を持つ「海の町」として広く知られていますが、実は三方を山に囲まれた「山の町」でもあります。
三ヶ根山、遠望峰山(とぼねやま)・聖山(ひじりやま)・五井山(ごいさん)・砥神山(とがみやま)・御堂山(みどうやま)・・・、蒲郡の人々は、古くから山と生活を共にしてきました。
古墳時代〜中世の熊野信仰〜明治の観光開発など蒲郡の山に関する歴史・文化・観光に目を向けた展示となりました。
展示目玉は、当館としては平成10年(1998年)の公開以来、26年ぶりに公開の県指定文化財「木造十一面観音立像」でした。(※令和6年度時点)
※平安時代後期の作と推定され、1957年に県が有形文化財に指定しています。
県指定文化財「木造十一面観音立像」搬入の様子を公開中→https://www.city.gamagori.lg.jp/site/museum/juichimenkannon.html
蒲郡市制70周年記念企画展「蒲郡の“市”宝 文化財指定絵画展」
10月19日(土曜日)から12月1日(日曜日)
特別展示室
蒲郡市内の社寺には建造物・仏像・古文書・書画等、多くの文化財が伝わっています。
そのうちの一部は当館に寄託されており、温度・湿度の変化が少ない収蔵庫内で大切にお預かりしています。
今回の企画展では、蒲郡市ゆかりのお宝を、至宝ならぬ“市”宝と銘打ち、文化財に指定されている絵画資料14件をご紹介しました。
蒲郡市制70周年記念企画展「がまごおりとみかん展 〜がまごおりは何故みかんが有名なのか〜」
令和7年2月15日(土曜日)から3月23日(日曜日)
特別展示室
蒲郡市の特産品として、今や全国にその名が知られる「蒲郡みかん」。その歴史は古く、江戸時代の文書に「蜜柑」の文字が登場します。
また、明治時代には神ノ郷(かみのごう)で穫れたみかんが「神ノ郷みかん」「西郡(にしのこおり)みかん」として、近隣では知られた存在でした。
しかし、蒲郡のみかんが全国的な知名度を得るためには、多くの困難を乗り越えてきた歴史があったのです。
企画展では、みかんを作り続けた蒲郡のみかん農家、そして、みかん栽培を牽引した蒲郡市柑橘農業協同組合の歩んだ歴史を紹介しました。
そして、みかんを含む蒲郡の農業を支える人材を数多く輩出した、宝飯郡立西部農学校(のち蒲郡農学校、現在の県立蒲郡高校)の貴重な資料も展示しました。

 情報をさがす
情報をさがす